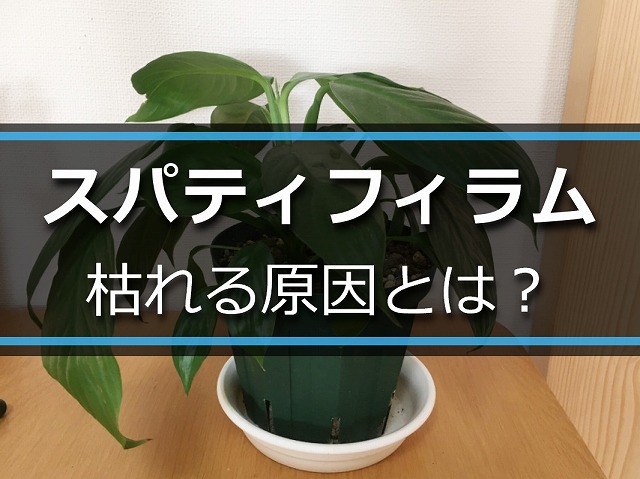艶やかな葉と個性的な形の白い花がエキゾチックなスパティフィラム。
開花期間も5月~10月と長く、葉だけでなく花も楽しめるのが人気の秘密です。
耐陰性が強く、室内で育てやすいスパティフィラムですが、枯れてしまう原因とは一体何なのでしょうか?
今回は、スパティフィラムの葉先だけが枯れる原因と対処法、株が弱ってしまう原因について紹介します。
スパティフィラムの葉先が枯れるときのチェックポイント
スパティフィラムの葉先が枯れる場合、まずは根詰まりしていないかを確認しましょう。
葉先が枯れる主な原因は乾燥ですが、2年以上植え替えや株分けをしていない場合、根がダメージを受けていることが多いです。

スパティフィラムは水不足で葉先が枯れやすい。ただ、根が傷んで水が吸えなくなってる可能性もあるんだ。
2年以上植え替えや株分けをしていないと、鉢内が蒸れて根が傷む

上写真は大株になったスパティフィラムを鉢から取り出したところです。
よく見ると、子株が集まって株元や根がぎゅうぎゅうに詰まっています。

根詰まりしていると水分や養分を根がスムーズに吸い上げられない。水やりしても、葉先が枯れたり、葉のハリが戻らなかったりする場合、根が傷んでいる可能性が高いんだ。
スパティフィラム 根詰まりの症状

- 葉先が枯れる
- 小さい葉ばかりになる
- 花芽が出てこない
- 下葉が変色する
- 水やり後、水分が土になかなか浸みこまない(以前よりも時間がかかるようになる)
- 鉢底から根がはみ出る(根がはみ出ていなくても根詰まりしているケースもある)
- 2年以上、株分けしていない
スパティフィラムは親株のまわりに株を増やしながら生長していく植物

上写真は大株のスパティフィラムです。よく見ると葉の先端が茶色く枯れています。

スパティフィラムは2年以上株分けしないと、株元が根で詰まって根詰まりを起こしていることが多いです。

スパティフィラムは親株のまわりに子株を増やしながら生長していくよ。
理想は年に1~2年に一度の株分けを兼ねた植え替え(4月~6月頃が適期)
 ▲大株に見えたスパティフィラムは小さな株の集合体でした
▲大株に見えたスパティフィラムは小さな株の集合体でした
2年以上株分けしていない場合は、生長期初期にあたる4月~6月頃に株分けして株元の詰まりを解消してあげます。

株分けしたらそれぞれの鉢に新しい用土で植え付け、たっぷりと水やりしたら風通しのよい半日陰で休ませましょう。

しっかりと根付くまでは過度の乾燥に気を付けます。
スパティフィラムは空気中の水分が多い状態を好むため、こまめな葉水もおすすめです。

葉先が枯れたり、葉が小さくなったり、花が咲かない…なんて場合も、根がダメージを受けている可能性があるよ。
☆★スパティフィラムの元気がない時の原因と対処法【症状別】↓↓

スパティフィラムの葉先が枯れる原因と対処法
スパティフィラムは観葉植物の中でも珍しく、比較的に水を好む植物です。

スパティフィラムは、ゴムの木やサンスベリアなどと同じような水やり頻度だと水切れを起こしやすいよ。
10度以下の寒さ
スパティフィラムは寒さに強くありません。元々が熱帯地方の植物のため、耐えられる温度は5度程度までです。
とはいえ、それは枯れないための最低温度。スパティフィラムの美しい姿を保つためには、最低でも10度は必要です。
夜になったら窓から1~2m離して冷気を防ぐ!

室内であっても気を付けなければならないのが冬場の窓際です。昼間は暖かくても、夜間は急激に冷え込むことの多い窓際。
冬は夜になったら窓から1~2mほど離し、できればお部屋の中心部に移動させ、朝になったら窓際へ戻してあげるのが理想です。
特に戸建ての場合、暖房を消した後の夜間は想像以上に冷え込むことも多いため、室内であっても油断は禁物ですね。

夜間の水やりもできるだけ控えよう。鉢内の水分が朝晩のうちに冷え込んで、根を冷やし株を弱らせてしまう恐れがあるからだよ。
☆★スパティフィラム 冬のお手入れ方法のポイント3つとは?↓↓

過度の乾燥
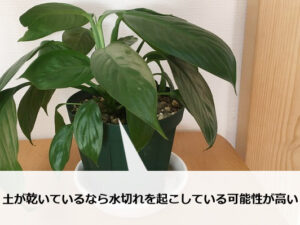
スパティフィラムは他の多くの観葉植物に比べて水を好む植物です。気温が15度以上になる生育期は土の表面が乾いてきたタイミングでたっぷりと水を与えましょう。
葉が垂れるのは水が足りていないサインです。すぐに水を与えれば葉がシャキッと元に戻るはずですよ。

乾燥状態があまりにも長く続くと、葉先が茶色く枯れ込むことが多いんだ。
気温が15度以下になったら水やりを控え目にシフトしよう
スパティフィラムの生育適温は20度~25度程度の暖かい環境です。そのため、気温が15度以下になる秋から冬場はスパティフィラムの生長がほぼ止まる時期になります。
そのため、暖かい時期と同じ感覚で水やりしていると根腐れを起こす原因になります。もし、水やりのタイミングが分からなければ、「葉が垂れたらすぐ水やり」でも構いません。
または、家庭用水分計を活用するのもおすすめですよ。(下写真)


土に挿しておくだけで土の乾き具合を測定して、水やりのタイミングを色で教えてくれる便利アイテムだよ。「これだけは枯らしたくない」という植物に使うのもおすすめ!
☆★観葉植物好きなら必ず持っておくべき!優秀すぎる園芸アイテム【厳選】↓↓

水のやり過ぎによる根腐れ
スパティフィラムは比較的に水を好みます。とはいえ、水のやり過ぎは根腐れを招き、株を枯らす原因になります。

水を好むけどやり過ぎはよくないって、一体どうしたらいいの?
そこで、ここからは時期別で具体的な水やり方法をご紹介します。
- 最低気温が安定して15度以上…土の表面が乾いてきたらたっぷりと水やり。水やり後はしっかりと水気を切って受け皿の汚れた水もこまめに捨てる。風通しのよい半日陰で管理。根詰まり・株詰まりしていない場合、ハイポネックス等の液体肥料を水に薄めて月に1~2回水やりとして与えるのもよい。葉水(はみず)を与えるのもよい。
- 最低気温が15度以下…土の表面が乾いて1~2日ほどしてから水やり。暖かい時期よりも水やりの間隔を少しずつ空けることで樹液濃度を高め耐寒性をつける。タイミングが分からない場合は葉が垂れたタイミングでの水やりでもok。空気中の湿度が低下しやすいため1日数回の葉水を行う。


2年以上植え替えや株分けをしていない場合、根詰まりを起こしていることが多い。まずは植え替えや株分けで根の詰まりを解消すること。根詰まりした状態で水を与えると、根がスムーズに水分を吸収できず、そのまま傷んで腐る恐れがあるんだ。
大株に見えても実は小さな株の集合体となり株が詰まりすぎていることも多い
 ▲大きく育ったスパティフィラムですが…
▲大きく育ったスパティフィラムですが…
上写真は一年前に植え替えをしたスパティフィラムです。ただ、株分けは2年以上していません。
去年植え替えをしたばかりなので、鉢底から根がはみ出ている様子もありませんでした。
 ▲株の内部を見ると親株のまわりに子株がびっしり!
▲株の内部を見ると親株のまわりに子株がびっしり!
しかし、鉢から株を取り出して株の内部を見たところ、親株のまわりにびっしりと子株が付いて根が絡み合っている状態でした。
そのため、株元がぎゅうぎゅうに詰まって花芽はもちろん、新しい葉も小さく形の歪んだものばかり出るようになっていたのです。
 ▲大株に見えていたが実は小さな株の集合体と化していた
▲大株に見えていたが実は小さな株の集合体と化していた
このように、スパティフィラムは親株の周りに子株を増やしながら生長していく植物です。
根詰まりした状態を放置し続けると、生育がスムーズに進まないだけでなく、鉢内の水はけが悪くなることで根腐れを招き枯らせてしまう事態にもなりかねません。
 ▲株分け後のスパティフィラム
▲株分け後のスパティフィラム

スパティフィラムを2年以上株分けしていない場合、春から秋にかけての暖かい時期に株の詰まりを解消してあげると生育がスムーズに進むことが多いんだね。
☆★花が咲かないスパティフィラムを株分けします【随時更新】↓↓

直射日光による葉焼け
スパティフィラムは直射日光をあまり好みません。特に気を付けたいのが夏場の高温期です。
暑い時期は直射日光により葉の一部が焼け焦げる「葉焼け」を起こしやすいからです。
スパティフィラムと同じくサトイモ科の観葉植物(ポトスやモンステラなど)は、「直射日光が苦手」という共通点があるのですね。
 ▲葉焼けしたポトスの葉は茶色く変色しています
▲葉焼けしたポトスの葉は茶色く変色しています
葉焼けした箇所は元に戻せない…
残念ながら、すでに葉焼けを起こした葉や花を元に戻すことはできません。
また、葉焼けした部位は光合成ができなくなるため、葉焼け面積が広がると株自体をも枯らす原因にもなりかねないのです。
 ▲葉焼けと乾燥と暑さで弱ったサトイモ科のシンゴニウム
▲葉焼けと乾燥と暑さで弱ったサトイモ科のシンゴニウム
葉焼けの症状には、「葉の色が薄くなる」「葉の一部が茶色くな焦げる」などです。
葉焼けの症状に気付いたら、できるだけ早く場所を移動させ、心配なら遮光ネットを利用します。
 ▲場所を移動し栽培方法を変更して復活したシンゴニウム
▲場所を移動し栽培方法を変更して復活したシンゴニウム

異変に気付いたら早目に対処することで、被害を最小限に抑えられるんだね。
病害虫
夏から秋のあいだに「ハダニ」「カイガラムシ」「アブラムシ」などの害虫が付くことがあります。
これらの害虫がスパティフィラムに付くと、吸汁により株を弱らされてしまいます。
葉が変色していたり、なんとなく全体の色つやが悪い場合は小さな虫が付いていないかも確認しましょう。
そのままにしておくと被害がどんどん拡大し、そのまま枯らされてしまうこともあります。
葉がベタベタする場合、カイガラムシが付いていることがよくある
 ▲モンステラに付いたカイガラムシ
▲モンステラに付いたカイガラムシ
特にカイガラムシは種類が非常に多く、上写真のような茶色の粒々に見えるものもあれば、下写真のように白い粉状の形態をしているものもあります。

葉がベタベタとする場合、カイガラムシの排泄物の可能性があります。
樹液を摂取するカイガラムシは糖分を含む排泄物を出すためベトつくのです。葉の付け根や裏、茎などをくまなくチェックしましょう。
早目の駆除が被害を最小限に抑えるコツです。

葉がベタベタとしていたら、まず「カイガラムシ」を疑おう。カイガラムシやハダニは、葉の表面だけでなく葉の裏や付け根・茎などにも潜んでいることが多いよ。
☆★観葉植物の害虫対策と駆除方法!虫を防ぐために押さえておくべきポイント3つ↓↓
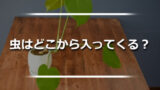
スパティフィラムの葉先が枯れる原因と対処法【まとめ】

今回は、スパティフィラムが枯れる主な原因と対処法をくわしくご紹介しました。
スパティフィラムが弱っている場合、まずは寒さに当たっていなかったか確認してみましょう。室内の場合でも油断は禁物。暖房を消した朝晩に冷え込んでいることが多いからです。特に窓際ですね。
次に土の状態を確認し、カラカラに乾いているなら水を与えて様子をみます。土が湿っているのに元気がない場合は根腐れが疑われるため、その場合は水やりを控えて風通しのよい場所に置きましょう。
また、うっかり夏場の西日に当たってしまわないよう気を付けてください。スパティフィラムを含むポトスやモンステラなどサトイモ科の観葉植物はとにかく「強すぎる光」で葉焼けを起こしやすいからです。

上写真のように、葉の色が抜けたように薄くなるのも葉焼けの初期症状です。
スパティフィラムが枯れる主な原因と対処法
- 10度以下の寒さ
- 過度の乾燥
- 根腐れ
- 直射日光による葉焼け
- 病害虫
スパティフィラムのその他topics